
呼吸が適切に行えることでのメリット
ボクノジム高円寺店代表トレーナーのそうです!
呼吸は、生きるうえで最も基本的な生命活動の一つです。しかし、日常の中でその質について意識する機会はあまりありません。
適切な呼吸ができているかどうかは、単に「息ができているか」だけではなく、身体の働き全体に深く関わっています。
この記事では、酸素供給量・pHバランス・腹腔内圧(IAP: Intra-Abdominal Pressure)の3つの側面から、呼吸が正しく行われることで得られる身体へのメリットを、科学的根拠に基づいて解説します。
合わせて読みたい:意識的な良い姿勢は腰痛を引き起こす
「2ヶ月後の健康よりも1年後の健康を」という理念から、怪我や病気から一番遠い場所へ導くためのボディメイクを提供します。
高円寺店詳細はこちら
1. 酸素供給量の最適化
人間の体内では、呼吸によって取り込まれた酸素が肺で血液に取り込まれ、全身の細胞に届けられます。
呼吸が浅く速い(いわゆる胸式呼吸が優位)状態では、肺の換気効率が低下し、ガス交換が十分に行われなくなる可能性があります。
特に、横隔膜を主導とした腹式呼吸では、肺の下部まで空気が入りやすく、肺胞での酸素と二酸化炭素の交換効率が高まります。
これにより、動脈血中の酸素飽和度を適切に保ち、組織への酸素供給が安定します。
酸素供給量が最適化されると:
-
細胞レベルでの代謝が正常化
-
持久力・集中力の向上
-
筋肉や内臓への血流改善
-
疲労の軽減
といった生理的メリットが得られます。
2. pHバランスの維持
体内のpHは、生命維持において極めて重要です。
人間の血液の正常なpHは 7.35〜7.45 の間に厳密に保たれており、この範囲を逸脱すると、酵素反応や代謝に障害が生じます。
呼吸は、このpHの調整に直接関与する機能を持っています。
人は呼気として二酸化炭素(CO₂)を排出しますが、このCO₂は血液中で炭酸(H₂CO₃)として存在し、pHに影響を与えます。
呼吸が浅くなりCO₂の排出が低下すると、血液が酸性に傾く(呼吸性アシドーシス)。
逆に過換気などでCO₂が過剰に排出されると、アルカリ性に傾く(呼吸性アルカローシス)。
適切な呼吸を維持することで、CO₂の排出量が調整され、血液のpHバランスが安定します。これは、神経系や筋肉の正常な活動にも必須の条件です。
3. 腹腔内圧(IAP)と姿勢・体幹安定性
腹腔内圧(IAP: Intra-Abdominal Pressure)とは、横隔膜・腹横筋・骨盤底筋・多裂筋などによって構成される「腹腔」の内部圧力のことを指します。
IAPは、呼吸と密接に関わっており、横隔膜が適切に上下することでIAPが形成され、体幹の内側から安定性が得られる仕組みになっています。
IAPのメリットとして以下が挙げられます:
-
脊柱の安定性向上:脊柱を内部から支える力が働き、腰痛予防にもつながる
-
姿勢保持力の向上:重力下での直立姿勢を無理なく維持しやすくなる
-
排便・排尿・分娩などの内臓機能の補助
逆に、呼吸が浅く胸式優位になっている状態では、IAPがうまく形成されず、姿勢の崩れ・腰部への負担増加・体幹の不安定性につながることがあります。
呼吸は「筋肉活動」でもある
呼吸は自律神経によって無意識に行われますが、実際には多くの筋肉が関与する能動的な運動です。
主な呼吸筋には以下があります:
-
横隔膜(主呼吸筋)
-
肋間筋(胸郭の拡張・収縮)
-
腹横筋・腹斜筋(強制呼気・IAP形成)
これらの筋肉が適切に連動し、正しいタイミング・強さで働くことで、効率的な呼吸が可能になります。
また、慢性的に呼吸が浅いと、これらの筋肉の過緊張や使いすぎが起こり、肩こりや首のこりなどの筋骨格系のトラブルの原因にもなり得ます。
まとめ:呼吸は全身の機能と直結している
呼吸が適切に行えるということは、単に肺を使うだけではありません。
それは、酸素供給の質を高め、体液のpHを安定させ、姿勢を内側から支えるための圧力を形成する行為です。
とくに現代人はストレスや座りすぎなどの影響で、呼吸が浅くなりがちです。
その結果として、代謝の低下・体幹の不安定・神経の過敏化といった問題につながる可能性があります。
呼吸は唯一、自律神経の働きに対して意識的に介入できる生理機能です。
正しく丁寧に呼吸することは、身体と心の健康を整えるための基本であり、誰でも今この瞬間から取り組むことができます。
ぜひ呼吸というものに意識を向けてみてください。


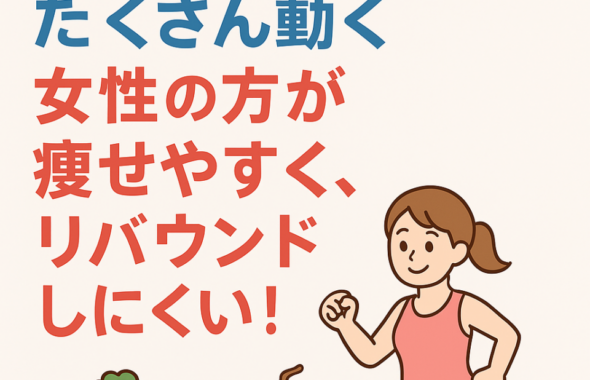


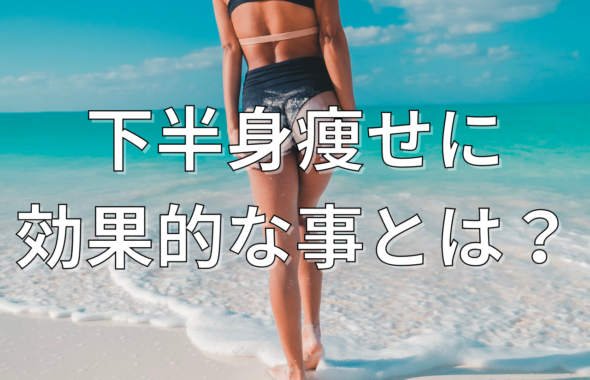

この記事へのコメントはありません。